ギターを弾いていると、“アドリブ演奏”をする場面って出てきますよね。
とりあえず、ペンタトニックだけでなんとなくできるようにはなったんだけど…そこから中々うまくならない!
そこで、次のステップとして“コードトーンを意識して弾きましょう”という事をするのがおすすめです!
ただ暗記するだけ…だけどコードトーンを覚えてしまえば、アドリブを弾く上でかなりの武器になりますよ!
単純な話なのにこれが難しい。
メリットとして以下のようなことが考えられます。
- 音を外しにくい
- 単純にアドリブの幅が増える
- コードトーンとそれ以外の音の選択肢ができるので演奏に緩急をつけられる
では実際どういう感じで覚えるのか?具体的な部分を考えてみました。
コードトーンの覚え方は2つ
まず、ギターでコードトーンの覚え方として2つのやり方があると思うんです。
- 指板の音の関係と形として覚える
- ひたすら音名を覚える
基本的には“形”か”音名”の2つです。
ギターは“形”で覚えるというのが主流だと思うのですが、僕はこの方法が逆にダメでした。
ずっと”形”で覚えていたのですが、”音名”を頭の中で歌うようにしたら、『こっちの方が楽に弾けるな〜』となりました。
なので、”形”でひたすら覚えている人で、中々うまく弾けないという人は“音名での暗記も進めていくといいかもしれません”。
自分の得意な方でやるのがいいと思いますが、両方やるのがおすすめです。
ではこれら2つはどういう風に覚えるのか解説します。
指板の音の関係を形で覚える
ギターは6本の弦ありそれぞれ決まったチューニングをされています。
つまり弦と同士のインターバルが決まってます。
基本的には同じフレット上にある音は隣同士の弦が”4度”の関係になっています。
ただし、3弦と2弦の間だけ長3度の関係になってします。
開放弦の隣り合った弦の関係を見てみましょう。
- E…ミ ↓P4
- B…シ ↓M3/↑P4
- G…ソ ↓P4/↑M3
- D…レ ↓P4/↑P4
- A…ラ ↓P4/↑P4
- E…ミ /↑P4
さらにフレットは右に1フレットずれると半音の関係になっています。
これを元に指板の位置関係を判別させて覚えてしまいます。
覚え方はコードフォームを覚えるのと似ています。
コードのベース音になるルートの音を元に3つの位置で覚えます。
- 6弦ルート
- 5弦ルート
- 4弦ルート
それぞれどこがなんの音になっているのは覚えてしまいます。
6弦ルート
試しに6弦ルートをの位置関係を2つずつみてみましょう。
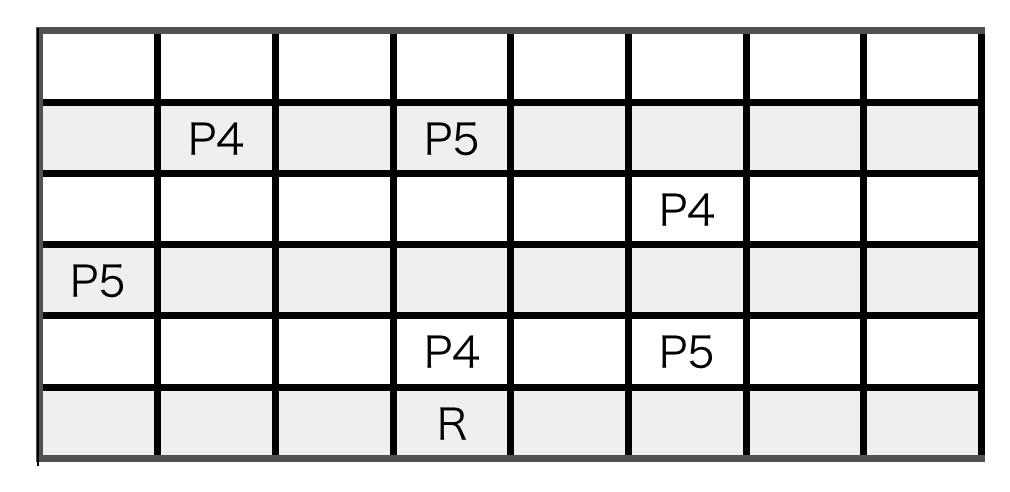
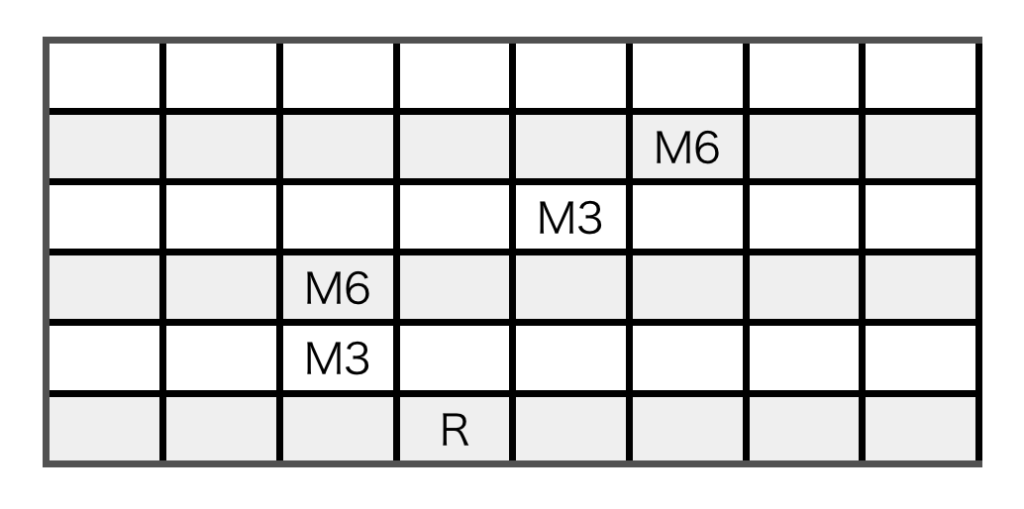
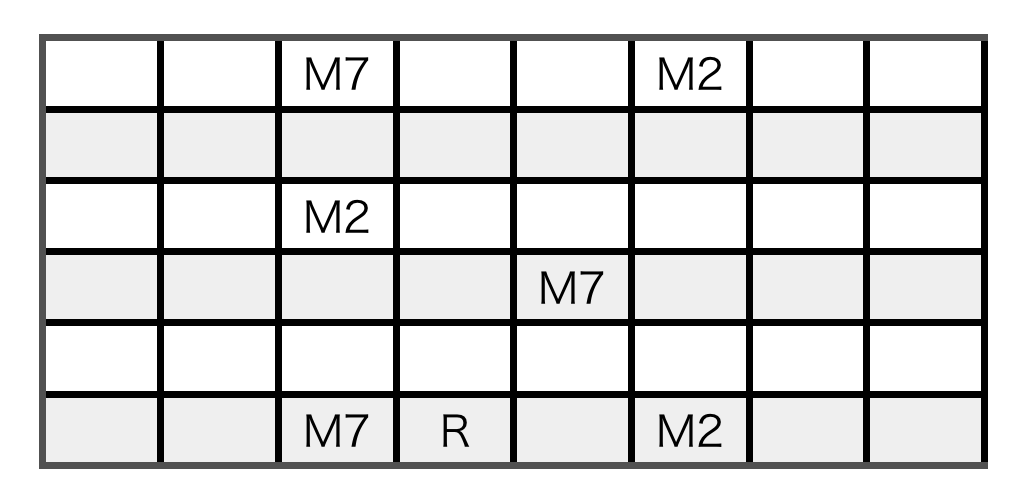
メリット
こちらの覚え方のメリットがあります。
- 移動ドの感覚ですぐに弾ける
- 視覚的にわかりやすい
デメリット
デメリットとして…
- 常にルートの音→目的の音という2工程が必要
- 元になる音から指板をみているため、実際に弾く音を見失ったりすることがある
- ルート音中心の音使いになりやすい
若干頭の回転が必要なイメージです。
またコード間の共通音を2つの指板の位置をイメージしてから、同じ音を探すのとっさにわかりにくいというのも感じます。
音名で覚える
音名を覚えるというのは読んで字のごとく“「CM7」のコードトーンは何の音か?”というのを覚えてしまいます。
この方法を使うにはまず“指板の音名を覚えている必要”があります。
「ドレミ」で覚えていくのですが、僕の場合は臨時記号を含め「ドディレメミファフィソサラリシ」で覚えています。このことについては別記事にまとめてあります。
話を戻して、CM7であれば「ドミソシ」
C7なら「ドミソリ」
…という風に全部暗記してしまいます。
メリット
- 他の楽器でも使える知識になる
- フレーズなどが覚えやすい
- 共通音がわかりやすい
デメリット
- キーチェンジに弱い
- 指板を全て暗記してなければならない
- コードがたくさんあるので、覚える量が多い
歌えるようにする
もしコードトーンを覚えて弾けるようになってきたら、なるべく歌うようにしましょう。
ルート音に対してハモれるようになると音自体をイメージするのが楽になります。
どういう音を出したいか?というのが明確にイメージできるようになるので、実際のフレーズ指や頭で考えるというより”音”優先で感覚的にフレーズを作れるようになります。




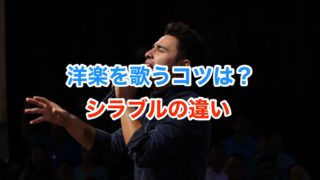



















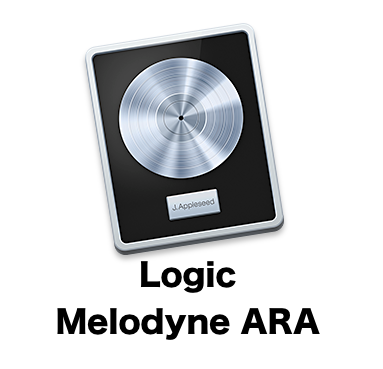


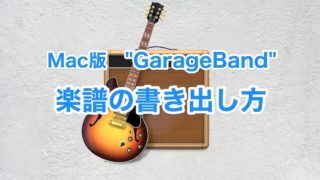
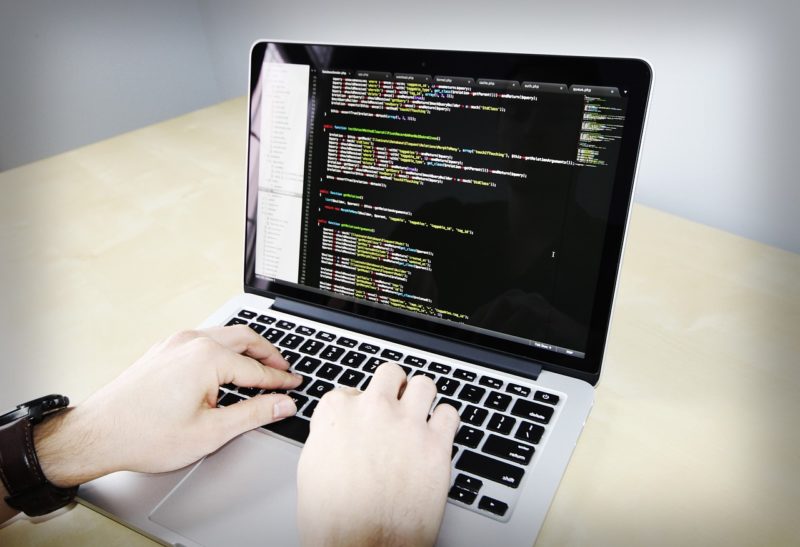
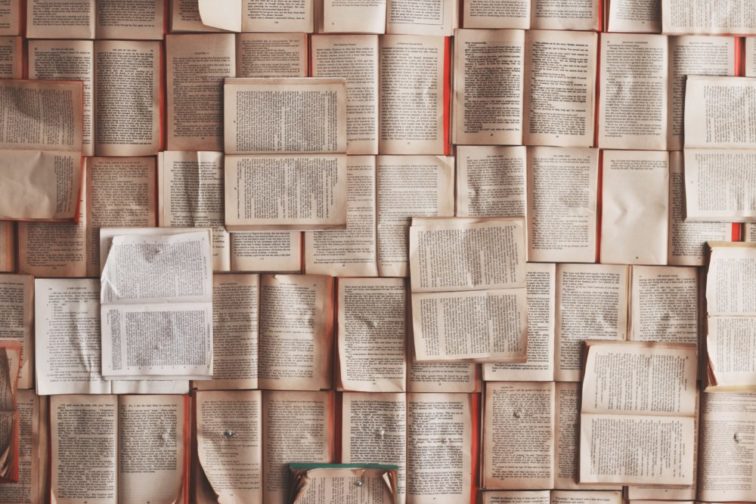
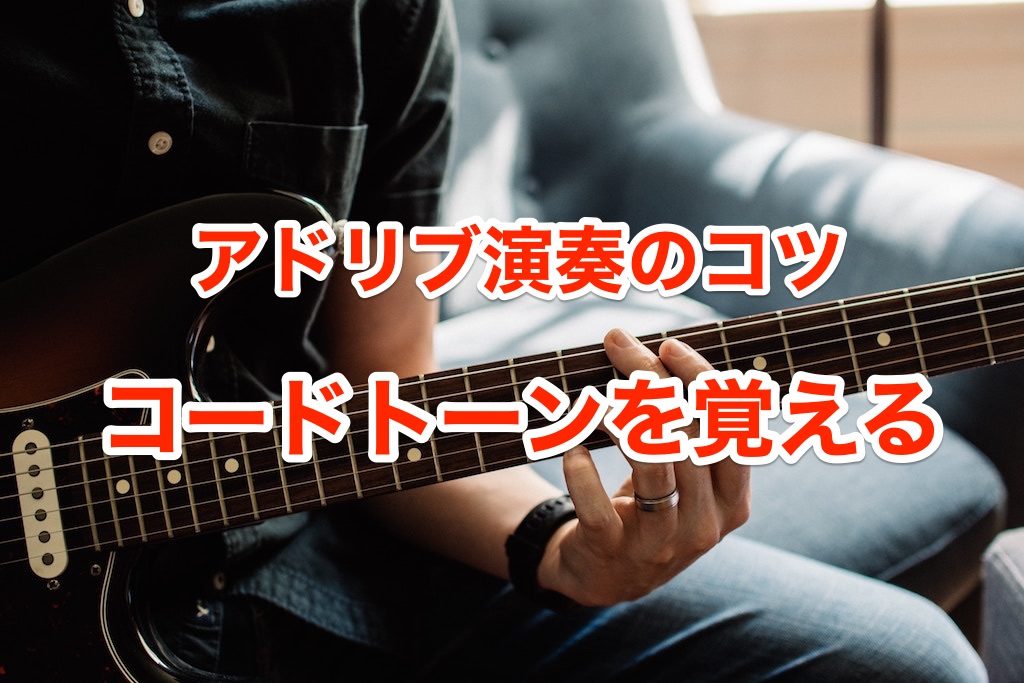


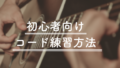

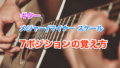
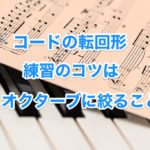

コメント